春の祭典 ━2006年━
2004年9月に行った「SOLO-ist」の後、次の公演を一刻も 早く行いたい欲求に悶々とした。今、この歳にしか表現出来ないものが消えてなくなってしまうような気がしたからだ。しかしこの間に僕は「The WILL」という無比のグループを持っていた。前回公演から1年9ヶ月、僕にとっては待ちに待った新作公演が6月に迫っていた。3月後半、プログラムにストラビンスキーの「春の祭典」を The WILLで演奏するという案が頭に浮かんだ。これは凄い。もしそんなことが出来たら・・・、と想像しながら震えた。早速、譜面を取り寄せ解読するが僕には到底分からない。これは剛君と深町さんに頼るしかないと考えた。
次のリハーサルの時、「春の祭典」を The WILLで演奏したいと2人に話した。しかし深町さんは「無理だ」と即答した。「50人のオーケストラのために書かれた曲を3人にアレンジして成功するとは思えない」と。更に「やるからには絶対に成功しなくてはならない。」とも言った。思いついてからそれまで、かなり盛り上がっていた僕としては予想しない答えに深く落胆した。「それより1人でやれば。以前の SOLO-ist でホルストの "惑星" をやってたじゃない」
2003年の「SOLO-ist」"Romanticism" で ホルストの交響曲「惑星」を断片的に流し、ソロをするという試みをしていた。

深町さんのこの提案を受け、しばし考え、やることに決めた。「春の祭典」の "序奏" から "大地の踊り" までの8曲を断片的に流し、その間をドラムソロでつなぐ方法で僕にしか出来ない「春の祭典」を考えた。20分の大作となり、譜面は何ページにもなった。

ところが当日、劇場入りした深町さんが僕に「ホリ、譜面を見ないで出来ないの?」と言う。
「それはちょっと・・・」と戸惑っていると、
「僕や剛は3歳から譜面を見てきているから譜面を見ながら弾くのが当たり前だけど、ホリはせいぜい20歳からでしょ。ホリは譜面なんて置かないで自由に演奏した方が絶対良いよ。」
時に深町さんはそれが良いと思えばそれまでどれほどの準備や積み重ねをしたかなど関係なく、捨てることを選択する。僕にはそれが怖いところであり、ドキドキするところである。
そしてプリントアウトした1枚の紙を渡してくれた。「これはバルトークが音楽のあり方、生演奏のあり方について講演したときのものだよ。読んでみて。」
以下はその全文です。
「もしもラジオによる芸術音楽の放送によって、音楽会に一度も行ったことのない人々や、行こうともしない人々に、音楽会に行ってその場で音楽を聴こうという要求を、ささやかなりと
も呼び覚ますことが出来るのでしたら、ラジオ放送は本当に有用な事業であると言わなくてはなりません。それでもなお、私は、ラジオのこの点での有用性が他のいっさいのマイナスの効果によって打ち消されてしまってはいないかと思うのです。
音楽を聴く立場から考えるとき、ラジオ音楽は、大衆の人達がお座なりで気まぐれな音楽の聞き方に慣れてしまう上で、大変な役割をはたしていると考えられます。なぜなら、ラジオのダイヤルをあちらこちらに調節したり、スイッチを入れたり切ったりすることがいとも簡単にできる上に、ラジオを聴きながら、他のことをしたり、おしゃべりをしたりすねことさえ出来るからです。多くの人にとっては、芸術音楽の放送さえもが、何かなま暖かい湯に愛撫されているようなものか、あるいは、なにかコーヒー店の音楽のようなものにほかなりません。音楽にはほとんど耳すら傾けることもなく、他の仕事ができるだけ飽きないでやれるようにと、背景でざわめいたり、鳴り響いたりしているものに他ならないのではないかと思われます。
-------------中略-----------------
生命のあるもの全て、瞬間から瞬間へと変わります。一方、機械で録音された音楽は、変化することのない姿に固定されてしまいます。私達の楽譜は、周知のように、作曲家が作品に思い描いている姿を、不十分な形で紙に書き留めたものです。ですから、作曲家が意図していることや想像していることの一切を、ほとんど完全な正確さで記録できる機械があるという事は、楽譜の不十分さを補うものとして大変意味のあることです。しかしながら、作曲家自身が、自分の作品の演奏者として登場するとき、彼は、彼自身の作品でありながら、いつも決して同じようには演奏しません。なぜでしょうか。それは他でもなく、彼が生きているからです。永遠に変化することこそが、生物の持っている最も自然な特性だからです。
ですから、ある作曲家の作品が、たとえどのように完全な取り扱いと完璧な方法によって録音されたとしても、それが、その時々の作曲家の想像によって演奏されたものである以上、絶えず録音だけでその作品を聴くことは決して薦められることではありません。こうした聞き方は時とともに作品を飽きさせるからです。また、作曲家自身でさえ、自作をある時はいっそう美しく、またある時はさほど美しくもない姿で演奏するといった具合に、その時々によって違ったふうに演奏することがありえるからです。
まったく同様のことが作曲家だけでなく、演奏家についてもいえます。こうしたことから、想像しうる限りの最も完璧なグラモフォンでさえも、生きた自然な音楽に完全に取って変わることは決してありません。機械音楽が、将来ある時期に、たとえば私たちが久しく、映画劇場にむなしく期待しているようなものと同じ様な、何か独自な価値あるものを想像しうるということは、十分考えられることです。もしそうであれば、いずれにしても、私たちにとって、多くの利益をもたらしてくれるでしょう。ですが、もしも、工場製品が手工業を荒し回ったのとちょうど同じように、機械音楽が本来の音楽を犠牲にして、世界中に蔓延るようになれば、まさにこの時、渦が始まると言えるでしょう。
私たちの後に続く世代の人々が、この渦から守られんことを祈りつつ、これで私の講演を終わります。」

その夜の公演から、僕の前の譜面台が消えた。思えば5年前に、今やジャズ界のカリスマと言われる菊地成孔氏をゲストに迎え始めた「SOLO-ist」の1作目は、パフォーマンスとして成り立つかどうかすらわからない不安に満ちたものだった。あれから5年という歳月を経て、この "Truth" は僕が初めて演出をしたと胸を張って言える作品になった。そこには僕が敬愛する渡辺剛と深町純という2人のアーティストとの出会いが不可欠だったと確信している。
以下は公演後、僕のホームページの特集に寄せてくれた深町さんのコメントだ。
「SOLO-ist」はユニークなパフォーマンスだと思う。まずそこには、パフォーマンス全体を支配する堀越君の強い(言葉による)メッセージがある。このひとつの精神的な支えを中心として、オブジェとダンスと音楽のコラボレーションが展開する。構成され演出されたステージもパフォーマンスの重要な一部をなしている。たぶん堀越君の目指しているものは、ある種の総合芸術なのだろう。 その目指しているものの香りは、あくまでも「日本」だと僕は信じたい。
「日本」なるものを定義するのは簡単ではない。なぜなら現代の「日本」という文化は迷走しているからだ。もちろん、その「迷走」そのものが日本の似姿だという逆説も成立するだろう。
明治維新以後、僕達は故郷の香りを失っていると思う。数日前、国立博物館に伊藤若沖という江戸中期の絵師の展覧会を見てきた。ここにある世界は、紛れもない日本文化そのものだ。艶やかで大胆でありながら、どこか冗談のような洒脱さを持っている。
挑戦し続ける堀越君に、もし課題があるとしたら、ふと力を抜く「粋」の存在だろう。もちろんこれは彼だけの問題ではない。僕自身も含めた日本の全ての音楽家の課題でもあるのだ。
「SOLO-ist」はその名の通りソロ・パーフォーマンスである。それゆえ形態が変幻自在であることも意味する。何が最善であるのか、それに向かって限りなく前進することを僕は期待して止まない。
深町 純
写真は公演後のロビーでコメントしている深町さん。

この公演にあわせて「The WILL」のファーストアルバム"INFINITY ORCHESTRA" が発売になった。それは僕にとって宝物のようなCDになった。
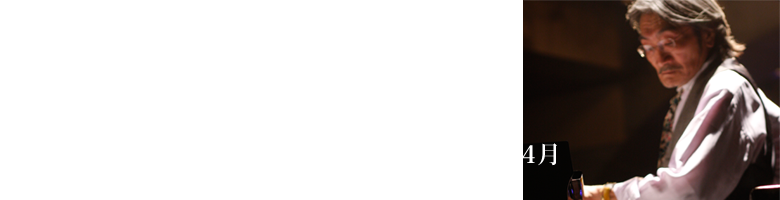
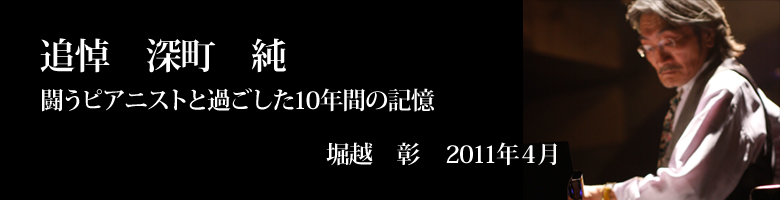
 2005年
2005年