The WILL 結成 ━2005年━
バイオリン渡辺剛、ピアノ深町純、ドラム堀越彰、この3人はとてもスケールの大きなバンドになる、と思った。そこで「3人にして無限大のオーケストラ」というキャッチコピーを思いついた。そしてバンド名を「The WILL」に決めた。"意志" や "志し" または "遺言" という意味が3人の音楽に対する妥協のない想いの強さにマッチしていると思い気に入った。新曲を持ち寄りリハーサルをした。剛君と深町さんそれぞれと僕のホームページ上で対談も行った。

演奏曲は以下の通り。出会った切っ掛けとなったピアソラの組曲「Tango Ballet」もやった。演奏はまだミスが多く満足するには程遠い出来だったが、何とも言えないスリルとスケールがあった。特に剛君と深町さんの2人で演奏したラフマニノフの「VOCALISE」は僕が今まで聴いたどの「VOCALISE」よりも抑制された美しさを持っていた。
1st ---------------------------------
1 Escualo(Astor Piazzolla)
2 Perucucion Interna(Akira Horikoshi)
3 Pathos(Tuyoshi Watanabe)
4 PianoSolo Prelude 4番(Chopin)
5 Tango Ballet(Astor Piazzolla)
- イントロダクション
- 街
- 出会い忘却
- キャバレー
- 孤独
- 終曲 町
- 天使の死
2nd ---------------------------------
1 Anomalocaris (Jun Fukamachi)
2 DrumSolo Truth(Akira Horikoshi)
3 ViolinSolo Pedal(Tuyoshi Watanabe)
4 Purple Haze(Jimi Hendrix)
5 VOCALISE(Rachmaninoff)
6 Sing Sing Sing(Louis Prema)
7 WAR CRY -鬨の声- (Akira Horikoshi)
EN 弔いの鐘(Akira Horikoshi)
ライブの後、僕はホームページで特集を組んだ。その中に深町さんが印象的なコメントをくれた。
正直に言って、まだ「The WILL」についてまだ言うべき事は多くはない。なぜなら、このバンドはまだほんの生まれたばかりの新生児のように、その可能性の大きさに比べて、為したことはあまりに小さいからだ。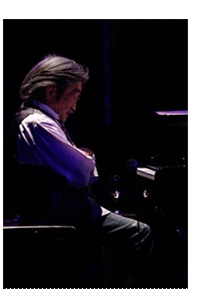 現在の日本の貧しい音楽状況にあって、こういうバンド、つまりインストゥルメント(器楽演奏、あるいは歌がない)という構成と、平易な意味での娯楽性を排除した姿勢は、受け入れられる場の極めて少ない。つまり商業的に成功するということはもちろん、多くのスタッフに支えられてのライブの継続すらままならないものだ。
現在の日本の貧しい音楽状況にあって、こういうバンド、つまりインストゥルメント(器楽演奏、あるいは歌がない)という構成と、平易な意味での娯楽性を排除した姿勢は、受け入れられる場の極めて少ない。つまり商業的に成功するということはもちろん、多くのスタッフに支えられてのライブの継続すらままならないものだ。
僕はずいぶん前から、「音楽が商品になった時から(音楽から)何かが失われた」と主張してきた。音楽が商品となった最大のキッカケはレコードというメディアの登場である。つまり1900年の初め頃であるから、ちょうど100年前のことだといえる。あるいは、ラジオ放送というものが始まったのも、ちょうど同じ頃ヨーロッパで1903年に、テレフンケン社が創立され鉱石ラジオの普及が始まったそうだ。エジソンが初めて録音機を作った時、最初に録音したものが、彼自身の歌う「メリーさんの羊」であったことはよく知られた話であるが、詩や小説の朗読でもなく、また著名人の演説や自然の音でもない、「歌」であったことは、レコードというもののその後を象徴した話である。
もちろん「音楽」そのものの歴史はかなり古い。今手元に資料がないので正確なことは言えないが、おそらくあのピラミッドを作り上げたほどの、高度な文明を持ったエジプトに音楽がなかったとは思えない。それならば紀元前二千年、つまり4千年も前の話だ。あるいは中国の歴史が六千年というなら、音楽の歴史もまた同じようなものだろう。人間の文化の歴史を見ると、文明というものに音楽は必ず内在されていたからだ。また、こういう民族音楽とは別に、バッハが音楽の父と言われるような音楽でさえ、彼の生まれたのが1685年であるから、3百年以上も昔のことである。
音楽が商品となった、ということの意味は、「聴衆」という人々の存在を生むことであり、音楽を聴くことが、一般の家庭や人々の日常生活に、必要不可欠なものになったということである。もちろん逆に言えば貴重な、大切なものではなくなってきた、ということでもある。 それまでの音楽家の誰ひとりもがしなかった、目前にいない仮想の聴衆に向かって音楽を演奏するようになり、かつてのどんな高名な音楽家も手に入れられなかったような、高額の収入を得るようになったということである。これで音楽自体に変化のない方が不自然というものだ。
それまでの音楽家の誰ひとりもがしなかった、目前にいない仮想の聴衆に向かって音楽を演奏するようになり、かつてのどんな高名な音楽家も手に入れられなかったような、高額の収入を得るようになったということである。これで音楽自体に変化のない方が不自然というものだ。
さて、「The WILL」は、その意味では古いタイプの音楽に回帰しようとしているかに思える。つまり、何よりも大切にしているのは、その音楽的な主張であるからだ。「主張を持っている」ということ は、かつての芸術というもののごく一般的な特徴であった。だから古いのである。僕はそれがまず気に入っている。その精神が居心地よいのである。同時に「The WILL」は骨董品であろうとはしていない。むしろ現代社会に受け入れられたいという、無謀とも思える望みを持って、そのためのささやかな努力を惜しんではいない。
だから、今生まれたばかりの新生児が何をしたかを問うのは、まだ時期尚早とも言える。「The WILL」がこの混濁した、腐れ切った逆境の中でどれほど生き続けられるか、つまり音楽活動を続けられるかが、まず僕たちが受けなければならない試練だと思う。 ぜひとも今後の「The WILL」の活動を、暖かい眼差しで見守ってくださることを、期待するばかりである。
深町 純
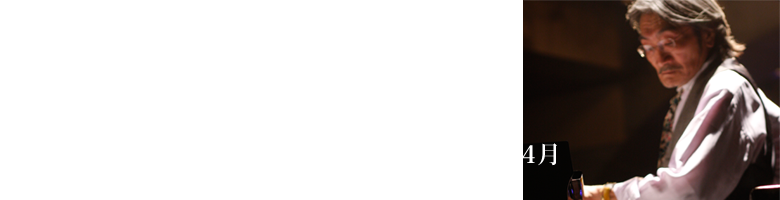
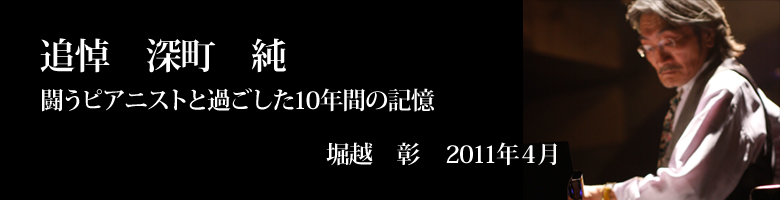
 2004年
2004年