
 |
|
|
ああ、月日の流れとは早いものです。あれから1カ月もたってしまいました。 4月24日、久し振りの「The WILL」のライブ。南青山マンダラにお越しいただい皆様ありがとうございました。 いらっしゃれなかった皆様、当日は「ラテンの歓喜と哀愁を込めて」と題し聴いていただきました。 以下が当日のメニューです。 |
 |
1st 2nd EN 天使の死 (Astor Piazzolla) |
| ラテンといっても僕たちなりのラテンアプローチですから、ハバネラあり、ボレロあり、フラメンコあり、ピアソラあり、プッチーニまでありの拡大解釈です。プッチーニは余計だろうって? いえいえ、今僕たちの心はイタリアに行きっ放しです。
なぜなら昨年末、イタリアのプログレッシブロックのサイトが主催する「プログアワード2006」にベストアルバム賞とベストプロデュース賞にノミネートされました。本戦は投票式で大賞はいただけませんでしたが、イタリアで発売もしていないCDに評価をしていただくとはなんと嬉しいことか。そもそもどうやって僕たちのCDがイタリアに渡ったのかさえわからないのです。 まもなくそのサイトにレビューが載り、楽しみに見てみると全部イタリア語・・・。そりゃそうですよね。よしっということで、こんなときに便利な翻訳サイトでイタリア語から英語、英語から日本語と訳したところ「・・・・・?」 散文詩のようになってしまいました。 例えば、僕が「The WILL」を結成したいきさつ |
|
|
13の年老年以来、それが典型的にはとりわけ彼自身接近するツールを演奏し始めたという東京の日本人ドラマー/彼女自身/主題のものおよびジャズ技術にそれ自体。バイオリンTsuyoshiワタナベの教師と一緒に、Red*Redソウル会社から、および教師および作曲家6月のFukamachi(計画とキーボード)に来て、それは、無関係で去らないこの仕事から始まるこのトリオを作成します。 |
|
続いて "弔いの鐘" のレビュー |
|
|
親密な雰囲気、微妙、Fukamachiからのある対位法で、それは、バイオリンが背景をジャズを踊る、より創造的な構造に面するその人の能力(古典 的ツール、純粋に)のフィールドから外に出るように見えるコースに彼を結び付けます。堀越(ドラムとゴングの間で)のソロの後、リスナーは、再び彼が素晴らしい形式中のFukamachiから大きなクラスと共に終了される憂鬱な大気の中で吸収されていたのを見つけます。 |
|
まあ当たらずとも遠からずという感じですが、これはちゃんと翻訳していただこうということになりました。 |
|
|
|
|
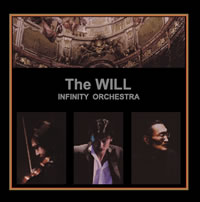 |
|
|
” The Will ” とは、単にひとつのバンドなのか、それともオーケストラか? はたまた天才の集団か? |
|
|
|
Rock-You という比較的小規模なレーベルのプロデューサーである木下一郎がこのアルバムを製作した。 |
| |
|
------ #1 War Cry (Akira Horikoshi)------------------------------ ------ #2 Escualo (A.Piazzolla)------------------------------- ------ #3 Passing Bell (Akira Horikoshi)------------------------------- ------ #4 Anomalocaris (Jun Fukamachi)----------------------------------- ------ #5 A Wall Wine Color (Tuyoshi Watanabe)-------------------------------------- ------ #6 Nessum Dorma ! (G.Puccini)------------------------------------------------ ------ #7 The Bolero (Akira Horikoshi)-------------------------------------------- ------ #8 Truth (Akira Horikoshi)----------------------------------------------- |
|
|
|
これはプログレッシブ・ロックだろうかと疑問に思う人もいるかもしれない。特定のジャンルに属さない音楽であると言えるだろう。しかし、音楽はすべてどこかのジャンルに属さなければならないのだろうか? この音楽は、聴き手が気づかないうちに、その気持ちを動かす。伝統的なルールに従わなくても、または新しい技を駆使しなくても、すばらしい音楽は生まれる。音楽家が奏でる音は、まっすぐ聴き手に届く。そこには「ジャンル」などという狭い文化的な背景は存在しないであろう。
|
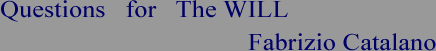 |
|
|
東洋、我々西洋人にとってまったく未知の伝統を持つ場所。 |
|
1. 2001年、舘形比呂ーというダンサーの公演で、3人は出会いました。リクエストはアストル・ピアソラのバレエ組曲「Tango Ballet」をたった3人で演奏することでした。私達はこの無謀なリクエストに躍動的で官能的なアレンジで答えることが出来ました。日々変化する即興性をも持って。その後、2004年に僕が主催、演出するパフォーマンス「SOLO-ist」に渡辺剛、深町純の2人を招聘しました。そのパフォーマンスで「WAR CRY」が生まれ、ユニットとして活動を始めました。音楽的には3人がそれぞれの楽器の限界を超え、フルオーケストラのダイナミクスを表現することがより追求されるでしょう。活動的には日本国内と同時に海外、特にヨーロッパの人々に僕たちの音を紹介して行きたいと思っています。
大野氏との出会いはこのアルバムにとって重要な要素の一つだと思っています。彼は日本の音楽の常に中心にいるエンジニアです。そして深町さんの旧友でもあります。その意味でももちろん信頼しています。大野氏は「ベーシストがいない分、バスドラムの音色とレベルアジャストに気を遣った」と言っています。僕からもリクエストをしました。例えば「Passing Bell」のドラムの音は日本の鐘の音をイメージさせたい、プッチーニの「Nessum Dorma!」は可能な限り音を制限し空間を作ることによりそこに荘厳なオーケストラストリングスをイメージさせたい、と。このバンドのキャッチフレーズは「3人にして無限のオーケストラ」ですが、大野さんの音作りは、3人の音を確かに「無限のオーケストラ」に導いたと思っています。
このアルバムで僕がやりたかったことは、1本の映画を見終わるように聴き終えてほしいということでした。特定の音楽的なカテゴリーを意識したことはありません。これまでに僕が経験し強くインスパイアーされた音楽はたくさんありますが、アルゼンチンタンゴ、フラメンコ、インド音楽、日本の伝統音楽、フリースタイルジャズ、クラシックなどは特にツアーやセッションに参加するチャンスがありました。その経験がThe WILLのサウンドを作ったとも言えるでしょう。 僕は音楽の中のドラムのポジションを変えたいと思っています。僕が表現したいのはフレーズやリズムパターンではなく、空間、雰囲気、現象。風が吹き抜けるようにシンバルを奏でたいし、波が押し寄せるようにクレッシェンドし鳥が舞い降りるようにデクレッシェンドしたいと思っています。それらの音に必然性をもたせることが僕にとってのチャレンジです。
僕たちの間には幾つかの共通点があります。ひとつは即興演奏に対する執着、もうひとつは日本人としての美意識を強く意識している所です。衝突はなかったですね。おそらくこれからもないでしょう。なぜならこのグループを進めるにあたり、決定権を僕が担っているからです。深町さんはそれを認めてくれています。我々はそれぞれのエゴにより解散していったグループをたくさん知っています。その二の舞は踏みたくないと強く思っています。
「The WILL」のDVDではありませんが、「The WILL」が活躍する僕のパフォーマンス「SOLO-ist」のビデオはディストリビューターが決まれば発売したいと思っています。「SOLO-ist」は音楽と美術の境界を超越した新たなるパフォーミングアートの提案です。動くオブジェと打楽器群が中心のパフォーマンスです。そこには「The WILL」の3人が出演しています。アルバム「INFINITY ORCHESTRA」に収録されている「The BOLERO」や「Truth」も含まれています。
渡辺剛の表現力に惚れ込んでいるからです。バイオリンじゃなければいけなかったわけではありませんが、渡辺剛じゃなければならなかった。それだけです。
このグループのコンセプトはフルオーケストラのダイナミズムをジャズの即興性、ロックの精神性で表現することにあります。そして僕が強く影響を受けた、ラフマニノフ、バルトーク、ピアソラなど偉大なる作曲家と "今" が出会う「音の交差地点」にしたいと考えています。
具体的にヨーロッパに行く予定はありません。ただ、このグループを作った時からの目的でもあるので、あらゆる可能性を求めて常に準備はしています。近い将来、ヨーロッパのオーディエンスに「The
WILL」のパフォーマンスを体験していただきたいと思っています。 |
|
堀越 彰 ”The Will ”のオフィシャルサイトhttp://www1.ttcn.ne.jp/play-ground/ |
|
|
|
Copyright(c) 2005 Akira Horikoshi. All Rights Reserved.
お問い合わせは info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp まで。 |