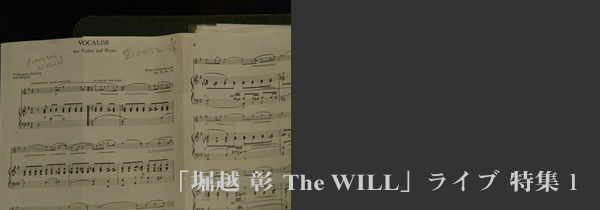
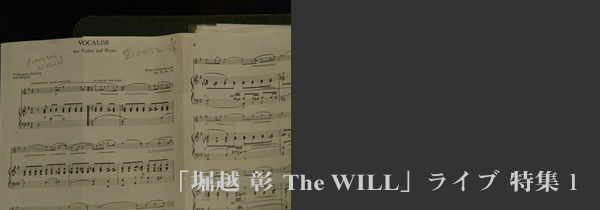 |
|
この3人の出会いは、2001年に行われた THE CONVOYの舘形比呂一のツアー「ソロプレイ2001」でした。今回はそのとき演奏したアストル・ピアソラの「タンゴ・バレエ組曲」を3年振りに再演します。ドラマチックなオーケストラアレンジをたった3人でダイナミックに再現するスケール感と感性、それがこのユニットの特徴だと自負しています。その他、3人の書き下ろしのオリジナル曲はもちろんクラシック曲のアレンジ等、エレクトリックとアコースティックを織りまぜ、渾身のパフォーマンスをお贈りします。 また、「SOLO-ist」同様、「The WILL」のステージにも何らかの形で単なるライブとは違う、アートパフォーマンス的なシーンをつくりたいと思っています。今回は3人を象徴する田中真聡の動くオブジェを南青山マンダラにも持ち込みたいと思っています。3機のオブシェがそれぞれ3人を象徴している。何を意味しているかはまだ言えませんが・・・。 では、6月29日、南青山マンダラでお待ちしています。 堀越 彰
|
 |
|
|
|
堀越 そんなわけで、「SOLO-ist」というパフォーマンスがこのグループの成り立ちに大きくかかわっていている以上、まず、「SOLO-ist」について剛君の感想を聞きたいんだけど、例えば去年の「SOLO-ist」公演に関してディスカッションをしたり、意見や感想を話し合ったりしたことがないよね。僕としてはそれを聞くのは本意ではないんだけれども、でも聞いてみたいなという気持ちもあって。 |
|
渡辺 堀越さんのものですよね、「SOLO-ist」は。だから、その堀越さん自身をあらわしているものを、堀越さんが考えている以上に引き出したり、逆に違った側面から光を当ててまた変化させてみたりとか、そういう楽しみはすごくありますね。でも、あくまでも堀越さんのものだというふうには思っているから、できるだけその世界をみんなが興味を持てる形でわかりやすく説明する役割があると思ってやっている。どうしても、一人で物を考えてつくると偏る部分があるじゃないですか。それはそれでとてもいいし、偏らないことはないはずだから、そこを、例えば「SOLO-ist」ならば、堀越さんが突き詰めていくべきだと思う。だけれども、周りが一緒になってそれを野放しで見ていると、お客さんとか出演者自身も入り込めない世界というのがあると思う。 |
|
だから、その堀越さんのやっていることに対していいなと思うところを見つけたら、それをできるだけほかの形で表現する、それが一番やっていて楽しい。でも、決して堀越さんから外れないようにするバランス、かといって、すべてを認めるわけじゃなく、という微妙なところを行きつつ、寄ったり離れたり重なったり、上に行ったり下に行ったりとか。 堀越 僕が剛君たちの「RED×RED Soul Company」に参加するというケースもあるわけで、かかわり方としては非常に似ていると思うんだけど、僕もまさに、例えばある一つの場面を表現しようとしたときに、それが二倍にも三倍にもなって膨らんだらいいなというところに力を注ぐ。いなくていいシーンは、全くいなくていいわけで、例えば「SOLO-ist」でも、僕がいなくて、渡辺剛がオブジェと絡んでいるシーンがあったりする。僕からすると、剛君に来てもらえばそういうシーンがつくれる楽しみがあるんだよね。「SOLO-ist」にゲストを呼ぶって、すごく難しくて、そもそも堀越彰と動くオブジェで成り立つようにつくっていて、そこにプレーヤーかダンサーか、もう一人アーティストが欲しいと思ったときに何を基準に選ぶかというと、オブジェと絡めて、僕とも並ぶことができる。さらに一人でもシーンを任すことができる。そんなアーティストって、少ないんだなと思う。 渡辺 すごく少ないと思います。今回、ほかのお仕事で堀越さんに絶対お願いしたいというアレンジをしたときもそうだけれども、一番キャスティングに気をつける。ただ単に自分の好みだけじゃなくて、好きだからといってお願いしちゃうのは、やはり危険なんですよね。好きなんだけれども、ここじゃないと思ったら、そこのシーンは切らないといけない。映画とか皆そうだけれども、とりあえず撮りたいところはばっと撮っていくんだけれども、一番大事な作業は編集だと思う。どこを切っていくか。できるだけ思い切って切っていかないと、どれだけそのシーンに思い入れがあって、例えば三日も四日もかけたのに、その三日かけたシーンは使えないとかね。言いたいことの本質をしっかり伝えるためには、どうしてもその作業は必要。だから、キャスティングって、一番大事だと思う。映画の編集なんかと同じで、それでほぼ決まりというところがあるよね。 堀越 キャスティングがうまくいったら、ほとんどうまくいくということってあるよね。 渡辺 いいなと思うところを引き出すために、例えばキャスティングするということも含めて、ねらいの外しも含めて、すごく重要だなと。「SOLO-ist」もそうだし、ほかの舞台もそうだし、なかなかいないんだもん。好きじゃなきゃだめだし、弾くことだけが好きでも困るから。 堀越 総合的に、例えば僕がこう叩いているときに隣でこうしていてほしいとか、細かいことだけれども、居方ってあるわけですよね。やはり一人一人が生き生きしていないと。バンドをやろうといったときに、一人一人が生き生きしていないバンドって、格好よくないじゃない。リーダー1人が生き生きしていても、他の4人がおつき合いという感じだと、バンドって格好悪いんだよね。やはり、僕があこがれたブリティッシュハードロックのグループなんかは、ボーカルがジャンプしてるかと思えば、うつむいて黙々とカッティングしてるギタリストがいたり、キャラクターがはっきりしていて、それぞれがそれぞれの世界で一人でも十分魅力的なんだよね。十代のころ、そんな自分の仕事を全うできるプレーヤーにとてもあこがれたんだよね。でも、その後、ジャズの世界からプロになって、ずっとそういうことを忘れていたような気がする。ジャズはもっと技術至上主義だからね。今になってようやく、「ああ、そのときにやりたかったことをやろうとしているのか」という感じで、何かとても楽しめる予感がする。 |
|
|
|
堀越 剛君といえばGクレフですが、僕、実は全然知らないんですよ。正直余り興味がなくて、やはり僕は今の剛君にすごく興味がある。ストイックにメロディーと向かい合っている今の剛君に興味がある。で、渡辺剛というアーティストの中にある音楽的構成要素は、クラシックがあり、民族音楽やポップス、ロック、あらゆるものが内在しているんだろうけれども、そのバランスというのはどんな感じなの? やっぱりクラシックが強いの? それともGクレフ的なものなの? 渡辺 結局、クラシックの作曲家の要素って、アレンジの要素がすごく強いんですね。特別な作曲家の特別なフレーズというのは、例えばモーツァルトにしてもバッハにしてもベートーベンにしてもあるんだけれども、時代とともに変化していくというのは、クラシックの場合はアレンジの仕方が変わっていっている。じゃ、そのテーマになっているものは何かといったら、昔はいろいろな規制があった中で、例えば宗教的なものだったり、パトロンに指定された題材だったり、王様をたたえる曲だったり。どんどんその題材から抜け出そうというのとか、例えば絵でいえば、影であった部分に光を当てようというのが音楽でもあって、その歴史の中でやがて朝が崩壊して、近代、現代と崩壊していって、その崩壊し終わったときに僕たちは育ってしまったから、そこに回帰しようという動きもあるんだけれども、Gクレフがやったのは、いわゆる現代音楽のおもしろさじゃなくて、やはり弦楽器のおもしろさ。だから、民族音楽的なものはとても得意だから、ジプシー的なメロディーにしたりとか。そのジプシー的な要素のピックアップの仕方というのは、クラシックの作曲家はすごく得意だから、ハンガリー舞曲にしても、ロシア民謡にしても、そこをすごくおもしろがってやっていた。僕の中では、クラシックは、小さいときからやっていたからあるんだけれども、やはり楽器を弾くところのおもしろさが融合したというところかな。クラシック要素以外には、どうしてもやはり日本の歌謡曲も入っちゃっている。 |
|
|
|
| 堀越 剛君が、例えば金谷さんのグループやいろいろなところでやるとき、日本の歌謡曲でも、クラシックの曲と同じようにトライするよね。どんなに今流行りの曲でも古い曲でも余り分け隔てなくとらえている。あれはすごく新鮮だったのね。
僕が、育った環境と言ったら変だけれども、洋楽しか聞かなかった子だから、子供のころは、日本の音楽はほとんど聞かなかった。ブリティッシュロックとか、アメリカンロックとか、そのうちやっぱりブルースだよなといって、ブルースをやって、その後、ジャズだよなといって、日本の歌謡曲からどんどん離れていったみたいな感じがあるのね。そのうちジャズも、実は自分のものとは思えなくて、十八、九ぐらいのときにいろいろ聞き漁って、これじゃないこれじゃないと探し求めて、それで民族音楽に行き着くわけ。当時はまだ余り聞いてる人もいなかったけど、アフリカンやインド、タンゴやフラメンコ、そういうところをやりたくなるわけ。できるだけネイティブなものがいい。その結果、日本やアジアをあえて意識したものをやりたくなるんだけど。ドラムセットを組むんでも、イメージは曼荼羅なんだよね。すべてが丸くて、それをさらに円に組んでいて、始まりも終わりもなく中心に自分がいる。千手観音の気分でセットの中心にいるんですよ。あくまでも僕の勝手なイメージなんだけど。そういう発想はすべて民族音楽からなんだよね。その辺の棒きれ拾って太鼓を叩くみたいな感じでドラムに向かいたいのね。そういう商品としてつくる音楽じゃない方向に行ったのね。でも今は、例えば「見上げてごらん夜の星を」とかやると、ああいい曲だなと思うわけ。だから、そういう曲に対する偏見はもはやないんだけれども、剛君を見たときに、ああやってメロディーに対して純粋にトライして、なおかつ作曲者の意図をも酌もうとしていて、そういう姿を見たときに、すごい新鮮というか純粋なものを感じたんだよね。 渡辺 メロディーは大好き。僕が弾いていて楽しいなと思うのは、どの音でも、どんなメロディーでも、メロディーとして弾くことによって、メロディーとして生かしてあげる作業が、好きだといえば好き。ラの音一つだけでも、コードが違えばメロディーになるじゃないとか。だから、クラシックをやりつつポップスの世界に入っていたときに、チープなメロディーというのはないような気がしたんですよ。何でかというと、歌の曲って、みんな好きで歌ったりするけれども、あれは歌詞を取っちゃうと、何だこりゃという曲が結構あるんですよ。言葉と一緒になっているから辛うじて音楽という、メロディーというものに認識するけれども、じゃ、歌詞を取ったら、ただの同じ音の羅列だったりする。ラップなんかもそうだけれども、あれはみんな音楽だと思うし、いいものを感じるときもあるじゃない。じゃ、そこには何の要素がプラスされているかというと、たった一つの音であっても、それを生かしてあげようという、生かすも殺すも歌手の力だったり、プレーヤーの力だったりする。だからかもしれない、分け隔てなくと聞こえてしまうのは。それは、演歌のメロディーであっても、シャンソンであってもクラシックのメロディーであっても、ジャパニーズポップスであっても、何も変わらないなというのはありますね。もう本当にプレーヤー次第。くだらないように聞こえるのは、プレーヤーが悪いだけ。 堀越 そうなんだ。 渡辺 だから、名曲と言われるようなクラシックの曲は、僕にとっては余り名曲じゃないのがいっぱいあるし、ほとんど聞かない。好きな曲が極端に少ないから。ジャズとかが好きになったのは高校時代ぐらいから、映画がきっかけだけれども。ばあって弾くだけじゃないよなと思う。弾くだけのは、全然おもしろいと思わないですよね。クラシックでも寝ちゃいますからね。やはりつまらないなと思って弾くだけのは、やはりつまらない。人が見えるというのが好きかな。 堀越 そうだよね。 渡辺 リズムがすごく大事だというのは、アメリカに行ったときに言われました。何はさておきリズムだよと、アメリカでは言いますよね。リズムとメロディーのバランス。ただ縦にそろえばいいというのじゃなくて、逆に言うと、縦にそろっているように聞こえればいいんだと思って。最初は、全然ドンカマのように弾いていたんだけれども、でも、そのとおりやっても、そのとおり合っているというように聞こえないときもある。ということは、人間の耳に合っているように聞こえればいいんだからと。それはすごく意識している。 バンドをやっていたときも、そういうのは学んだかもしれない。バンドって、特に僕たち学生バンドだったから、みんな下手っぴなんですよ、作曲にしたって。和声学はもちろん学校で学んでいるんだけれども、オリジナルのものって、和声学では整理がつかないじゃない。ものをつくるって、マニュアルどおりにつくってもちっともおもしろくなくて、プラモデルをつくっているみたいになっちゃうから、そうしたときに、みんな下手くそな作曲をするわけですよ。それをみんなでつくるときに、ここがおかしいよとか言いながら、結構言い合えた経験があるから、簡単に、それボツみたいな、ディレクターなんかにも、一生懸命つくったのに、剛、だめだよこれ、わかってないな、ポップスをわかってないよみたいなね。でも、みんなで一曲ずつアルバムに入れようといったときに、みんなで協力してつくった作業とか、足りないところは、じゃ、ベースラインが足りなかったんだとか、これはドラムのリズムがなってないんだとやっていくうちにでき上がったものが、ちっちゃいヒットだけれども、ヒットしたりする。CDが売れたり、ツアーをしているうちに、お客さんのアンケートですごく人気が出たりする。そうすると、自信がわいてくる。メロディーとかリズムとか自分がつくったものを、じゃ、何がそこに人と自分のオリジナルとの接点があったんだろうと。決してメロディーが長けているわけじゃないのにと思うわけですよ、自分で客観的に振り返ってみると。じゃ、アレンジがすごくよかったのか。いや、アレンジも自分としてはやっただけなんだけれどもなと。 堀越 人がいい曲と言うのは、優れいている優れていないじゃないからね。 渡辺 その好き嫌いに引っかかってくる。できれば、時代の波に迎合するんじゃなくて、あくまでもオリジナリティーを追求しながら、時代のどこかに引っかかるというのが一番幸せだし、それをあきらめたくない。 堀越 僕も同感。迎合するもしないも、そのすべを知らないんだけれども、迎合しようという気持ちは全然ないんだ。今やっていることをやり通していくうちに、時代の何かを取り入れたり、あるいは普遍的なものへ行き着いたりすればいいと思っている。 渡辺 かといって、今の曲、音楽をやらないというのはもちろん無理だし、そんなことは考えていないんだけれども。メロディーに対する考え方というのは、クラシックをずっと弾いてきたというのが特殊にあるのかなと思う。なのに、ポップスは嫌いじゃないから。そのポップスは嫌いじゃないというのも、ポップスが好きなわけじゃないんですよ、僕は。結局、クラシックを弾いていると、みんなが同じメロディーを弾くじゃないですか。再創造芸術みたいなところだから、そこにオリジナリティーは何かあるのかといったら、何もないんですよ。何もないんです。 |
|
堀越 でも、そこにメロディーに対する自分なりの表現の仕方というのはあるわけでしょう。 渡辺 それを突き詰めると、本人そのものなんだと思うんですよ。 堀越 そうだよね。そうかもしれない。 渡辺 プレーヤー自身、そのものでしかないから。 堀越 それを言ってしまうと、人となりが音に出るプレーヤーというのがおもしろいわけで、そういうプレーヤーを、僕は魅力的に思ったり、逆に嫉妬したりする。 渡辺 そうずっと思っていたんだけれども、あるとき、そこに自分の変な思い入れを入れるのをやめたんですよ。 |
|
堀越 それは、メロディーに。 渡辺 そう。例えば、クラシックの曲を、あの演奏家がああいうふうに弾いたから、そういうふうにやってみよう、でもあの演奏家と同じだと思われるのは嫌だから、違ったところでテンポを変えてみようとか、じゃ、こういうアーティキュレーションがあるんだけれども、僕はこういうふうに分けてみようとか、いっぱいやったんですよ。だけれども、結局何をやっても自分以外にはなれないことがわかったときがあったんですよ。どうしようもないなと思って、じゃ、自分らしく弾くのはやめようと。自分らしく弾くのというのはやめてもやめられないから、そこに入り込んでしまおうと。 堀越 いろいろ考えて、こうしよう、ああしようというのはやめようと。 渡辺 例えば、「川の流れのように」を弾くときに、僕なりの「川の流れのように」を弾こうというふうに全然思わなくなっちゃったんですよ。美空ひばりでいいやと。「川の流れのように」の音楽の中にいる僕でいいと。だから、みんなが知っている「川の流れのように」を弾こうと思って弾いているだけ。前だったらいろいろ弾いたかもしれないけれども、今は、みんなが知っている、歌いやすいように素直に弾いてあげようと思う。きっとそれが聞きたいはずだと。それを渡辺がやりたいように弾くことは、とても曲に対して失礼だなと。結局、聞いている人も入り込めない。だから、何でもそういうふうに弾くようになっちゃった。でもね、聞いた人がこれは間違いなく渡辺が弾いているってわかると言うんですよ。そう思ってほかのミュージシャンの弾いているのを聞くと、譜面どおりに弾いていても、間違いなくその人なんですよ。ジャズなんかでも、だれかのアドリブを完コピしても、その人じゃない、今演奏しているその人でしかない。そういう表現者の持つ力というのをすごく信用している。信用しつつ、どんなものであれ、オリジナルをつくった人とか、ちょっと言い方は大げさだけれども、尊敬している。 堀越 敬意を表しているというか。 渡辺 すごく尊敬できるなと。ここ五年、六年ぐらいですごく素直に尊敬できるようになった。だから、どんなものであれ、斜めに見ることができなくなって、できるだけまっすぐ入りたいなと。抵抗なくなった感じかな。そうやっているのが好きですね。 堀越 なるほどね。僕が演奏しているときに思うのは、予定を立てない、こう叩いたからこうなるという予定を立てないところに常に自分を置きたいと思う。真ん中の空間に自分がいて、三百六十度どっちにも、次の瞬間に変化できるという。それはその瞬間、自分がやる一番の務めで、それをもっと具体的に言うと、常にリラックスしていることとか、フォームのベースから始まりまたそこに帰るとか、頭の位置、肘の位置、腰の位置、ドラム的にいうといっぱいあるんだけれども、僕はそれを「Lotus Position」と呼んでいて、僕にとってのテーマでもあるわけ。要は、叩かなきゃいけないフレーズが一つもない、パターンが一つもない、その瞬間聞こえてきたものに対して自分がどうするかというのはその瞬間の自分しかわからないみたいなところにいて、そういう意味でのフラットさ、ニュートラルさを常に持とうとする。感情的になって、例えば悲しい曲を叩こうとか、あるいは怒りを表現しようとか、自分自身がその固まりにならないようにしてるんだよね。 渡辺 そういう感じしますよ、確かにする。堀越さんの場合は。だから、ほかと違う独自のスタイルになっているんだと思う。 |
|
(ALL Photo by Hideyuki Ozawa) |
| ということで、都内の某バーで行われた剛君との対談は果てなく続きましたが、話の内容が多岐にわたり、かなり専門的な話になってきたので、この辺で終わりにさせていただきました。颯爽とバイクにまたがって登場した剛君は、再び風のように帰って行きました。何て格好いいのでしょうか。僕が感じる剛君の印象は、「 Noblesse Oblige (高き身分の者に伴う義務)」という言葉があるように、他との比較ではなく、自分の価値観で自分を評価し、自分に課していく。深町さんもしかり。僕もそうであることを願う日々ですが・・・。 |
|
Copyright(c) 2005 Akira Horikoshi. All Rights Reserved.
お問い合わせは info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp まで。 |